|
|
| 構図・模様・配色を決め、その意匠に相応しい生地を選ぶ。 |
 |
 |
|
|
| 青花と呼ばれる液で下絵を描き、更に糊筒で糸のように細い糸目糊を下絵の線に沿って置く、または糸目型で糊を置く場合もある。この技術は友禅染めの中で最も難しい技術のひとつで友禅染めの特徴はこの糸目糊置にある。 |
|
|
 |
 |
|
|
| 豆汁(ごじる)を糸目糊置きされた模様の部分に挿すことで、染液が糸目の外ににじみ出なくなり、染料の浸透を助けムラを出にくくする |
|
 |
 |
|
|
| 酸性染料を主体とし、設計図案の通り、ムラなく糸目糊の外に出ないよう、丹念に色を挿す。 |
|
 |
 |
|
|
| 染着された生地を蒸し箱に入れ、摂氏100℃で40~60分くらい蒸す。染液が生地に着色させただけでは、まだ染料が生地に「染まった」状態ではなく、この蒸しを経て初めて「染まった」状態になる |
|
|
 |
 |
|
|
| 模様部分に次の引き染め工程で地色が入らないように、ゴム糊やデンプン糊で模様部分を伏せる。この防染で地色を入れる準備が整う |
|
 |
 |
 |
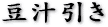 |
(ごじるひき) |
|
| ここで再び豆汁を引き、次の工程である引き染めのムラやにじみを押さえる |
|
 |
 |
|
|
| 刷毛で意図する染液を、生地に引いて染める。ここでの着色によって生地の地色が確定する |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
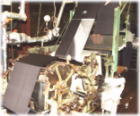 |
|
|
| この作業で蒸気を当ててシワを伸ばし、反物の幅や長さを揃える |
|
 |
|
|
| これで友禅加工工程は完了するが、細線の加筆の必要があるとき、金銀泥描き、擢疋田の加工、辻ヶ花染めなどの描絵もここで行う。 |
 |
 |
|
|
| 摺箔・金彩とも呼ばれ、「型紙による摺箔」「糊による筒描き」「切金切箔」「金砂子」の4種類がある。一般的に友禅に併用される刺繍は「菅縫い」「纏り縫い」「齣縫い」「相良縫い」などが多い。 |
|
|
 |
|
|
|
|

